営業活動におけるプロセスの中に、フォローという重要なステップがあります。
特に顧客との商談後のフォローを「後追い営業」と呼びますが、この「後追い営業」を苦手とする営業担当者がとても多いのです。
受注を獲得するためには必ずやらなければならないことですが、やり方を間違えると一瞬で顧客に嫌われてしまうという、簡単なようでなかなか奥が深いのが「後追い営業」です。
この「後追い営業」の必要性と、デキる営業担当者がどのような手段やテクニックを使っているのか、分かりやすくご説明していきます。
後追い営業とは
顧客との商談中に契約に至らず、「検討します」と言われて持ち帰りなることがあります。
その後、案件を眠らせず受注に結びつけるためにするのが「後追い営業」です。
後追い営業の手段
後追い営業の手段には、電話・訪問・メールなどがあります。
ここ数年は直接訪問しづらい状況が続いているため、オンラインでの商談も多く、後追い営業にメールを活用する営業担当者が多くなってきました。
メールは相手の都合のいい時に確認してもらえるため、積極的に活用したいツールです。
後追い営業は必要?
積極的なアクションを起こさなければ、最悪の場合には自社で受注できる可能性が高かった顧客を、他社に横取りされてしまう可能性があります。
また、他社からの切り替えを狙う場合は、顧客が今契約している他社の営業担当者に相談する可能性があります。
他社も顧客を取られないよう必死に防衛してきますので、タイムリーな後追い営業をすることが重要です。
後追い営業が失敗する理由
後追い営業はやっているものの、なかなか成果につながらない人が多いのはなぜでしょうか。
もしかしたら次のようなやり方をしていないか、後追い営業が失敗する理由について確認してみましょう。
進捗確認しかしていない
「検討します」という言葉を鵜呑みにして、いきなり「検討結果はいかがでしょうか」と切り出してしまうと、失敗する確率が高くなります。
まずは、前回のお礼を述べて、説明に不足がなかったどうかを確認します。
- 「先日のご説明の中でご不明点はありませんか」
- 「〇〇の部分について、きちんとお伝えできていたか心配でお電話しました」
不明点があればご説明し、不明点はないと言われたら「もしご契約について迷われている点があればお聞かせ願えますか」など、契約に関する話題を出しましょう。
ここで断られる場合もありますし、本当に前向きに検討していただけている場合は、ここで受注になるケースもあります。
「検討します」が断り文句であるのかそうでないのか、見込みの確度を正確に把握する力も必要になります。
決断を急がせてしまう
営業目標のことを考えると、つい決断を急がせてしまうことがあるでしょう。
ここで焦ると顧客も身構えてしまいます。
「鉄は熱いうちに打て」ということわざがありますが、「熱く」なってから打たないと意味がありません。
相手の気持ちが熱くなった状態をしっかりと見極めてから、クロージングに入りましょう。
一度断られたら、その後何もフォローしない
その時はニーズがなくても、その後の環境の変化によって必要になる時が来るかもしれません。
来たるべき時に備えて、継続的なフォローは必須です。
そうは言っても「また断られるんじゃないか」と思ったら、再度連絡するのをためらうこともあるでしょう。
そうならないために、断られた時に1つやっておくことがあります。
断られた時にそのまま話を終了させるのではなく、「またいい情報があったら提供させてください」とひとこと添えます。
これだけで、次に電話やメールを送る時の心理的ハードルが低くなります。
「見込みなし」の判断が早すぎる
相手の反応がいまいち良くなかったり、なかなかリアクションをもらえなかったりすると、「見込みなし」と判断してしまいがちです。
なんとなく反応が悪かった、電話をかけたけど出てくれない、メールの返信がないなど理由は様々ありますが、どれも個人の受け止め方によって基準が変わってきてしまいます。
何回電話したら、何回メールを送ったらのように、どのような状況になったら「見込みなし」と判断するのかという基準を社内で決めておくと、「なんとなく」というあいまいな感情で早計な判断することがなくなります。
後追い営業に罪悪感を持ってしまう
相手の迷惑になるのではと考えて、後追い営業に罪悪感を持ってしまう営業担当者はとても多いです。
相手を思いやるマインドはとてもいいことですが、相手の感情は相手にしか分かりませんので考えすぎは禁物です。
「うちの商品はいいものだから、ぜひお知らせしたい・使ってもらいたい」という営業活動は、むしろ顧客にとってプラスになるかもしれないことです。
まずは、自社の商品やサービスに自信を持つことが重要です。
デキる人はやっている受注につながる必勝テク
多くの人が苦手とする後追い営業ですが、中には得意としている人もいます。
そんなデキる人がやっている受注につながるテクニックをご紹介します。
2回断られてからが本番
ちょうどその商品が欲しかったという顧客でない限り、一度の商談で受注まで至るのは珍しいことです。
営業活動において断られるのは当たり前のことと受け止めて、後追い営業で地道にフォローを続ける必要があります。
先に述べた通り、1回目の商談で断られても「またいい情報があったら提供させてください」とお伝えしているので、情報提供を続けることで顧客と良好な関係が築ければ、いざ先方にニーズが発生した場合、1番先に声がかかる可能性が高くなります。
断られる理由を徹底分析し、あらゆるシナリオを用意する
後追い営業をする前には、必ず断られた場合のシナリオを用意しておきましょう。
自分が思い描いたストーリー通りに進まないのが営業ですので、断られる理由別に「こう言われたらこう切り返す」「こう言われたら一旦受け止めて日を改める」など、あらゆるパターンのシナリオを用意しておけば、あたふたせずに対応することができます。
「売ろうとしない」が必勝テク
「売ろうとしてる」と感じた途端、顧客の気持ちは一気に離れます。
営業なので売ろうとするのは当たり前のようですが、実はデキる営業担当者は売ろうとしません。
ひたすら顧客にとって有益な情報提供を続けて、チャンスが来るのを虎視眈々と待ちます。
そうするといつしか顧客にも「いつもよくしてもらっているから何かお返しがしたい」という感情が芽生えるようになります。
これを「好意の返報性」といい、人はいいことをされたらいいことで返したいという心理になるのです。
もし購入するとしたら、この人から買おうという気持ちになりやすくなります。
ふと思い出してもらえる存在になる
営業担当者にとって、顧客に忘れられないようにすることは非常に重要な課題です。
そのためには、電話でもメールでも訪問でもいいですが、定期的に顔を出すことが大切になります。
企業などがメルマガなどを配信するのには、そういう理由もあります。
困った時「あの人に相談してみようかな?」というように、ふと思い出してもらえる存在になれたら成功です。
雑談力を上げる
後追い営業において情報提供を続けることは非常に大切なことですが、自社の商品やサービスの話だけだと、どうしても途中でネタ切れになることがあります。
自社の商品やサービスと直接関係のないことでも、守備範囲を広くして調べておくと、意外なニーズを発見できることがあります。
また、採用や人材育成など、業種に関係なく多くの企業が悩む問題についても精通しておくと、話題が広がりやすくなります。
こうした専門知識だけでなく、たわいもない話が気軽にできるような雑談力を身に着けておくと、顧客との信頼関係が築きやすいというメリットもあります。
悩んでいる企業に対して、悩みを解決できる企業を紹介できるような人脈が構築できていると、なお良いでしょう。
中小企業診断士試験おすすめの通信講座
中小企業診断士のおすすめ通信講座を紹介します。低価格帯でコストパフォーマンスに優れたものがおすすめで、高価格帯の講座は含まれていません。
診断士ゼミナール

・詳しい解説付きの過去問題集7年分
・二次試験合格に必須の添削指導
・新しい暗記ツールの一次7科目穴埋めドリル
・合格お祝い金と3年間受講延長無料
スタディング(旧 通勤講座)

・AIを使った学習サポートが充実!AI学習プランは魅力的
・科目ごとの関係が明白な学習マップ
・AIによる実力スコア判定で成長を実感できる
まとめ
後追い営業において、デキる担当者のやっていることは以下のようにまとめることができます。
- 商談の後はお礼コール(メール)を始めとしたフォローを欠かさない
- 売り込むのではなく、あくまで顧客に有益な情報提供という姿勢で臨む
- 断られたら即見込み客からドロップするのではなく、長期戦を視野に入れた関係作りを継続する
- 自社商品だけでなく、多くの顧客に刺さりそうな情報について、常にアンテナを高くして収集している
上記のようなテクニックはもちろん重要ですが、顧客に寄り添った対応を心がけ、信頼を勝ち得るということが一番大切なポイントになります。

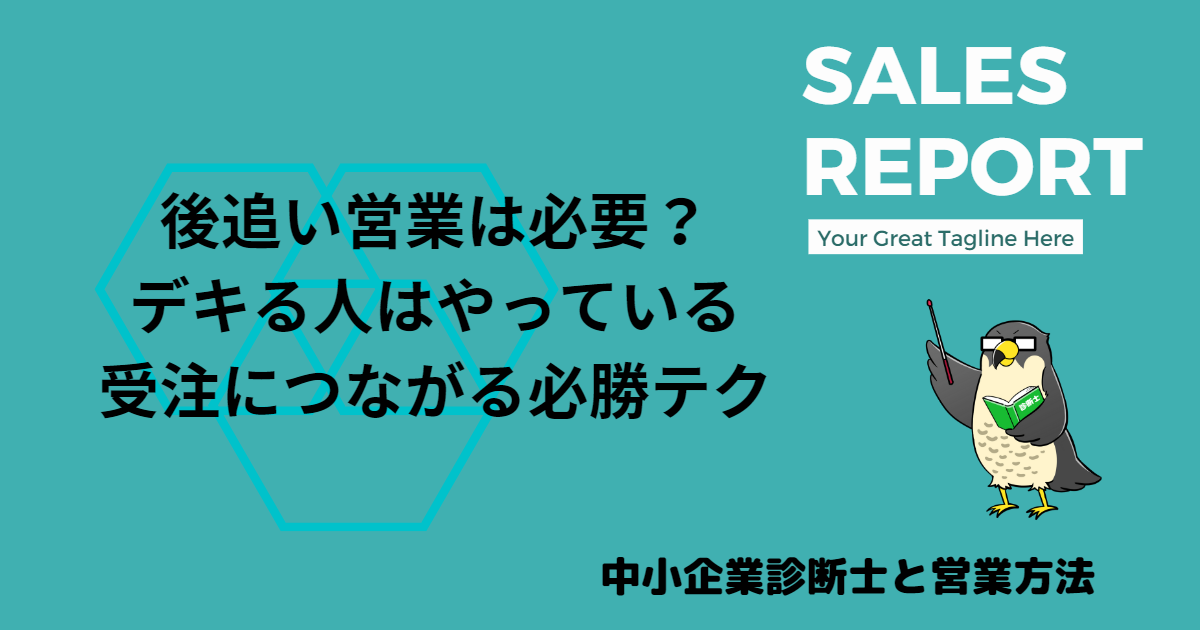
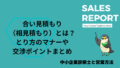
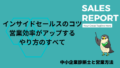
コメント