Googleをはじめとする海外の有名企業も導入している、注目の「OKR(Objectives and Key Results)」。簡単に言うと「目標管理フレームワーク」の一種ですが、なぜ注目されているのでしょうか?また、他の目標管理フレームワークとは、何が違うのでしょうか?
注目されているフレームワークなので、上位からの指示で自社でも導入するように指示がきたものの、知識がなく何を参考にすればいいか分からない方もいるでしょう。
そこでこの記事では、OKRの特徴や具体的な導入方法をご紹介します。
OKRとは?簡単に解説
OKR(Objectives and Key Results)は、直訳すると「目標と主な成果(成果指標)」です。言葉の通り、目標と成果指標から成り立っています。
OKRの仕組み
OKRは、1つの目標(Objectives)に対して、3~5個の成果指標(Key Results)を設定します。
目標と成果指標から構成される会社全体のOKRに基づいて、さらにチームや個人のOKRが存在する仕組みです。
会社全体の目標と個人の目標の方向性が一致している、という点が他の目標管理フレームワークと異なる点です。
OKRの設計方法
目標管理手法の多くで、100%達成できる目標を掲げますが、OKRでは達成することが難しい可能性がある野心的な目標を設定します。
チャレンジングでわかりやすい目標にすることで、メンバーのエンゲージメント(モチベーション、動機付け)が高まるのです。
OKRにおける目標は定性的であることが多い一方で、明確で測定可能な成果指標を設定することが求められます。
なぜOKRが必要なのか?OKRのメリットを簡単に解説
企業がOKRを導入する理由は何でしょうか?
OKRを導入する主なメリットとして、以下が挙げられます。
- 従業員のエンゲージメントが高まる
- 個人の殻を破り、予想以上の成果を挙げることができる
- 変化の激しい環境に適応できる
まず、会社の方向性と従業員の方向性が一致するため、従業員のエンゲージメントが高まることを期待できます。
OKRでは達成率が70パーセント程度のチャレンジングな目標を掲げるため、従業員が自分自身の殻を破り、予想以上の成果を上げることができるでしょう。
あえて100パーセント達成できない目標を掲げることで、たとえ完璧に達成することができなくても、過去よりも大きな成果をあげることが可能になります。
OKRは短いスパンで運用するため、他の目標設定管理の手法よりも、フレキシブルな調整や変更が可能となります。変化スピードがはやい環境にも対応することができるのです。
OKRとMBO、KPIを簡単に比較
OKRと混同しがちなMBOやKPIと簡単に比較することで、OKRの目的や特徴をより深く理解していきましょう。
OKRとMBOの違い
MBO(Management By Objectives:目標による管理)は、OKRよりも古い目標管理手法です。
2つは似ていますが、目標の設定方法や活用方法が異なります。
OKRにおいて、企業と個人の目標の方向性が一致するのに対して、MBOでは個人が別々に目標設定を行います。
会社全体の目標と個人の目標は必ずしも一致しないのです。
また、MBOは従業員の人事評価を行い、報酬を決定することを目的としています。
OKRは各自の報酬を決定することが目的ではありません。
報酬とは別に設定することで、より高い目標を掲げることが可能になります。
さらに、MBOが年間の目標を設定することで、1年単位で振り返りを行うのに対して、OKRは1か月~3か月の期間で目標設定や振り返りを実施します。
MBOと比較して、こまめな軌道修正ができる点もOKRの特徴です。
OKRとKPIの違い
KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は、目標を達成するための指標(目印)のことです。
KPIは、進行状況をモニタリングするためのもので、OKRとは役割が異なります。
また、KPIは目標を達成するためのフレームワークであるため、100パーセントの達成度を求められる、という点もKPIとは違う点と言えるでしょう。
進捗状況にあわせて適宜調整を行っていく必要があるため、レビューの頻度はOKRと同じか、もしくはそれ以上となります。
OKRの導入方法
実際にOKRを導入するためには、どのような手順で行えばいいのでしょうか。導入方法を簡単にご紹介します。
1.会社のOKRの設定
まずは企業全体のOKRを設定しましょう。
目標を明確に表明しておくことで、あとでチームや個人が目標を設定する際に、整合性を持たせることができるのです。
2.チームや各部門のOKRの設定
チームや各部門レベルの目標設定にあたっては、会社全体や他のチームのOKRとの整合性を意識すべきです。
必ずしも全ての組織のOKRを反映させる必要はありませんが、少なくとも他の1つのOKRには関連させましょう。
また、各チームのリーダーが集まって目標設定を行うなど、他のチームと調整を行いながら、設定をすることが大事です。
3.個人のOKRの設定
会社やチームのOKRと整合性をとりながら、個人のOKRを設定します。
これらが結びついていることで、組織の中で優先順位が高い業務に、各自が集中して取り組むことが可能です。
また、個人のOKRが他の従業員に共有されるため、コミュニケーションの活性化も期待できます。
4.高頻度のレビュー
四半期に1回の振り返り以外にも、チーム内での進捗確認や中間レビューを行うとよいでしょう。
定期的にOKRの進捗や課題などを確認することで、適切な目標に調整したり、課題解決を都度行うことができます。
5.四半期単位での最終的な振り返り
最後に結果の評価を行います。
四半期単位のサイクルで、OKRを運用することが多いです。
ポイントは、あくまで目標の達成度の評価であり、人の評価ではないことです。
目標の達成状況を明らかにして、次のOKRの設定に向けて検討します。
日本企業におけるOKRの導入事例
Googleなどの海外有名企業で導入されているOKRですが、一部の日本企業でもOKRが導入されています。
具体的な事例を確認しましょう。
メルカリ
メルカリは、他の日本企業に先駆けて、2015年にOKRを導入しました。
実際の運用としては、チーム単位でのOKRを、毎週または隔週で振り返りを行い、個人のOKRは、MTGや1on1の場で定期的に進捗を確認します。
個人の人事評価は、目標達成度ではなく、プロセスの中での成果やパフォーマンスが評価の中心です。
OKRを評価に結びつける際に「そもそも適切な目標設定ができているか」に気を付ける必要があります。
freee
オンラインでバックオフィス業務全般を支援する事業を展開するfreee株式会社では、
創業初期からOKRを導入しています。
まず数年単位での組織のOKRを設定し、チーム単位のOKRに落とし込んでいるようです。
個人のOKRは必ずしも設定する必要はありません。
OKRを導入する効果として、エンゲージメントサーベイでは、ミッションやカルチャーに共感する項目で高いスコアが出ています。
GMOペパボ
多数の個人向けインターネットサービスを展開するGMOペパボでは、2021年から全社でOKRを導入しました。
チーム単位でのOKRや進捗状況は、全社に公開されています。
GMPペパボでも、個人のOKRの設定は必須ではありません。
運用上の工夫として、OKRを実施するうえでの課題や改善方法等の情報共有をSlack上で行っています。
中小企業診断士試験おすすめの通信講座
中小企業診断士のおすすめ通信講座を紹介します。低価格帯でコストパフォーマンスに優れたものがおすすめで、高価格帯の講座は含まれていません。
診断士ゼミナール

・詳しい解説付きの過去問題集7年分
・二次試験合格に必須の添削指導
・新しい暗記ツールの一次7科目穴埋めドリル
・合格お祝い金と3年間受講延長無料
スタディング(旧 通勤講座)

・AIを使った学習サポートが充実!AI学習プランは魅力的
・科目ごとの関係が明白な学習マップ
・AIによる実力スコア判定で成長を実感できる
まとめ
OKRを導入することでエンゲージメントの向上など、ポジティブな効果が期待できます。
一方で、適切に目標設定をできないと、導入に失敗してしまうケースもあります。
今回ご紹介した具体的な運用方法や事例を、実践に役立ててください。

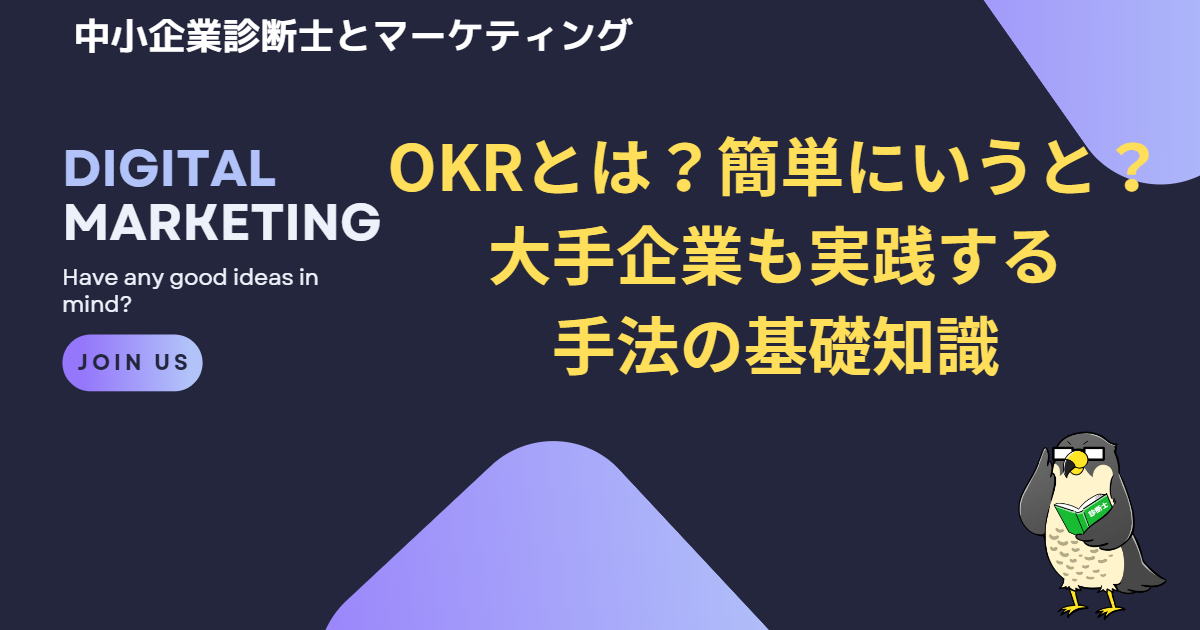

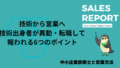
コメント