プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)分析は、事業を増やし多角化していくにあたって定期的に実施しておくべき分析です。しかし、自社の分析をどのようにし、その結果をどう活用していけばわからないこともあるでしょう。
PPM分析は適切に実施し、その結果をうまく活用することで、多角化戦略に対して経営資源の配分ををうまくコントロールできます。
そこでこの記事では、PPM分析についてその内容を確認し、PPM分析結果の活用法や有名な企業の事例を紹介します。PPM分析に取り組みたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
PPM分析とは?
PPM分できは、1970年にボストン・コンサルティング・グループが提唱したフレームワークです。
企業が持つ独立した事業を市場の成長率と相対的市場シェアの2つの観点で分類し、どこにどの程度の経営資源を分配するべきか判断するために用いられます。多角化した事業に対して、選択と集中の判断を行うためにも活用できます。
PPM分析を行う際に必要となる、市場成長率と相対的市場シェアについて、その概要と計算方法を解説します。
市場成長率
市場成長率は、前年の市場規模に対して、今年の市場規模がどのように推移したかを百分率で表現します。市場規模は、市場全体の売り上げ総額を用います。計算式は以下です。
今年の市場規模÷前年の市場規模×100
計算に用いる市場規模の情報ですが、各省庁や業界団体が発表していることが多いので、所属する業界の情報を入手して用いるのがいいでしょう。公表されているもので、だれでも入手できるものである方が、説明性が高くなります。
また、公開されていない情報を活用したい場合には、民間の調査会社が発行しているマーケットレポートを購入するといいでしょう。
相対的市場シェア
相対的市場シェアは、業界トップの他社の市場シェアに対して、自社の市場シェアが占める割合を表します。また、絶対的市場シェアは、各社が個別に求める市場シェアで次の式で表されます。
絶対的市場シェア=事業の売上高÷事業が属する市場全体の売り上げ総額
相対的市場シェア=自社の絶対的市場シェア÷他社の中で業界トップの絶対的市場シェア
情報の入手元として、他社の売上高は決算のタイミングなどで公表される財務諸表などのデータを利用するのが一般的です。また、事業が属する市場を選択するときには、どの粒度の分類で計算するのか明確にしておきましょう。
PPM分析の4つの事業分類
PPM分析では、市場成長率と相対的市場シェアの2つ軸を元に、事業を以下の4つに分類されます。それぞれについてどのように捉えればいいかを解説します。
- 金のなる木
- 花形
- 問題児
- 負け犬
金のなる木(シェア高×成長率低)
金のなる木は、市場競争が起きにくく、事業に積極的な投資が不要です。高い市場シェアを元に売り上げが期待でき、さらに投資を抑えることができるため、もっとも高い利益が見込める分類です。
金のなる木で得られた利益は、市場成長率が高くコストがかかる花形や問題児への事業投資に回すことで、高いシェアと利益を獲得していけるように取り組んでいくのが一般的です。
花形(シェア高×成長率高)
成長率が高いため、多くの企業にとって魅力的な市場になるため、多くの企業が高いシェアを獲得しようと積極的に参入、事業投資を行うため、競争が激しい市場です。その中でも高いシェアが獲得できているものが花形です。
自社はあらかじめ高い市場シェアを獲得できていますが、競争に打ち勝つために積極的な事業投資を行う必要があります。売り上げは多いですが投資資金の流出も大きくなります。シェアを維持できれば、市場の成長と共に利益が大きくなっていくでしょう。
問題児(シェア低×成長率高)
問題児は、花形と同様に市場成長率が高いため、シェアを獲得していくために、積極的に事業投資を行う必要がある市場です。現時点での利益は多くありませんが、シェアを獲得することで花形へ転換するため、金のなる木などで得た資金を投入していくことが多いです。
一方で、事業投資が多く必要になるため、市場シェアがなかなか獲得できず利益に繋がってこない場合には、思い切って事業撤退する勇気も必要です。
負け犬(シェア低×成長率低)
市場成長率も市場シェアも低い事業で、継続する意味があまりない市場です。ここにかけている経営資源は他に回す方が効果的なため、早い段階で撤退の決断をするといいでしょう。
また、問題児のシェアが取れずに市場成長性が鈍化してしまった場合、負け犬になってしまいます。投資した資金が無駄になってしまうため、問題児への投資は注意が必要です。
PPM分析の活用方法
PPM分析で、自社の保有事業を4つに分類した後、その結果をどのように活用すればいいのでしょうか?さまざまな活用法がありますが、ここでは代表的なものを2点紹介します。
事業を多角化すべきかどうかの判断
PPM分析を行うことで、自社の保有している事業が4つの分類のどのフェーズにあるのかを確認できます。その結果から、新しい事業を立ち上げ、多角化すべきかどうかの判断が可能です。
例えば、自社の事業が金のなる木しかないのであれば、市場成長性が期待できないので、問題児から花形を狙えそうな事業の立ち上げを検討します。また、現状問題児しかなければいずれ負け犬になってしまう可能性があるので、安定する事業を立ち上げるなどの選択肢があります。
このように、自社の現状を把握することで、今後事業を多角化すべきかどうか、どのような所を狙っていけばいいかの検討に活用できます。
多角化した事業に対する経営資源配分の検討
すでに多角化を行っている場合、どの事業にどの程度の経営資源を配分していくのかは、会社の行く末を決める重要なポイントです。そこで、PPM分析によって自社の事業がどの分類に置かれるのかを確認する必要があります。
金のなる木で得られた利益を、花形や問題児などに分類される事業に投資することで、高いシェアと市場拡大に伴う利益獲得が期待できます。また、負け犬に分類された事業は費用対効果が低くなっているので、徐々に資源の分配比率を小さくしていき、他の事業に振り分けます。
経営資源の投入方法としては、事業における新製品の開発や販路開拓、また人材の獲得や育成などがあります。成長していく市場で取り組む事業に対してこれらへの投資額を増やすことで、自社の成長が期待できます。
PPM分析のメリットとデメリット
PPM分析のメリットとデメリットについて解説します。
PPM分析のメリット
PPM分析のメリットとしては、事業分野の強化や撤退、維持などの経営判断に役立てたり、自社のおよび事業の将来性把握をしたりすることが可能です。また、競合企業との格差を可視化したり、経営資源の配分をする際の優先順位をつけやすくなったりすることも、メリットとなります。
入手がそれほど難しくない情報を元に、シンプルな計算で自社の現状把握や今後の参考になる情報が得られる点は、大きなメリットといえます。一度取り組んでみるといいでしょう。
PPM分析のデメリット
一方で、PPM分析のデメリットとしては、経験効果が働かない点やプロダクトライフサイクルの判断が正確にできない点が挙げられます。また、シナジー効果を考慮しておらず、判断基準が財務指標での視点となっているため、イノベーションの創出には向いていません。
事業構造が複雑な現代では、複数の事業が複雑に絡み合っていることで大きな効果を生み出すことが珍しくないため、PPM分析の結果だけを信じて取り組むのはリスクがあります。
PPM分析の事例
最後に、PPM分析を行った際の事例をソニーとキャノンの2社紹介します。いずれも有名な大企業なので、取り組んでいる事業がどこに位置するのか、イメージしやすいでしょう。
ソニー
ソニーは当初、AV機器メーカーとして成長してきました。ウォークマンなどのAV機器を多く販売し、世界でも屈指のブランド力を持っています。しかし、2000年以降はAV機器の販売、業績が低迷していました。
AV機器事業やパソコンブランドのVAIOが金のなる木から負け犬になってしまったため、VAIOの売却、AV事業の縮小により、経営資源を確保しました。それを金融事業やゲーム、音楽、プロダクト事業などの花形、問題児に分配することで、2015年には復活を果たしています。
PPM分析を行うことで、過去に利益を生み出していた事業の状況を適切に把握し縮小売却の判断をしたことが、回復に繋がっています。
キャノン
キャノンは、一眼レフ事業、コンパクトカメラ事業、ファクシミリ事業、ページプリンタ事業、インクジェットプリンタ事業などがあります。
一眼レフ事業やコンパクトカメラ事業は花形でしたが、スマートフォンの出現によって市場自体が大幅に縮小して、負け犬になってしまいました。一方で、ページプリンタ事業やインクジェットプリンタ事業は市場占有率が高く、花形、もしくは金のなる木に分類されます。
インクジェットプリンタ事業の競合が多く厳しいため、花形から問題児に移行する可能性があるため、今後はシェアを維持、獲得するために資源の投入が必要になるかもしれません。
中小企業診断士試験おすすめの通信講座
中小企業診断士のおすすめ通信講座を紹介します。低価格帯でコストパフォーマンスに優れたものがおすすめで、高価格帯の講座は含まれていません。
診断士ゼミナール

・詳しい解説付きの過去問題集7年分
・二次試験合格に必須の添削指導
・新しい暗記ツールの一次7科目穴埋めドリル
・合格お祝い金と3年間受講延長無料
スタディング(旧 通勤講座)

・AIを使った学習サポートが充実!AI学習プランは魅力的
・科目ごとの関係が明白な学習マップ
・AIによる実力スコア判定で成長を実感できる
まとめ
PPM分析について、概要や事例について紹介しました。PPM分析は、市場成長性と市場占有率の観点で4つのフェーズに分類することで、経営資源の配分を決定する際の参考になります。多角化した事業の将来を適正化できるため、すでに多くの企業で取り入れられています。
新規事業の構築や多角化に取り組む際には、PPM分析は欠かせない手法です。まだ取り組んだことがない場合には、必要な情報を集める時間を確保し、一度取り組んでみるといいでしょう。実際に取り組んでみると、想定とは異なる意外な結果が出るかもしれません。
想定と異なる結果が出た場合には、そこがチャンスに繋がる可能性もありますので、ぜひ一度取り組んでみてください。

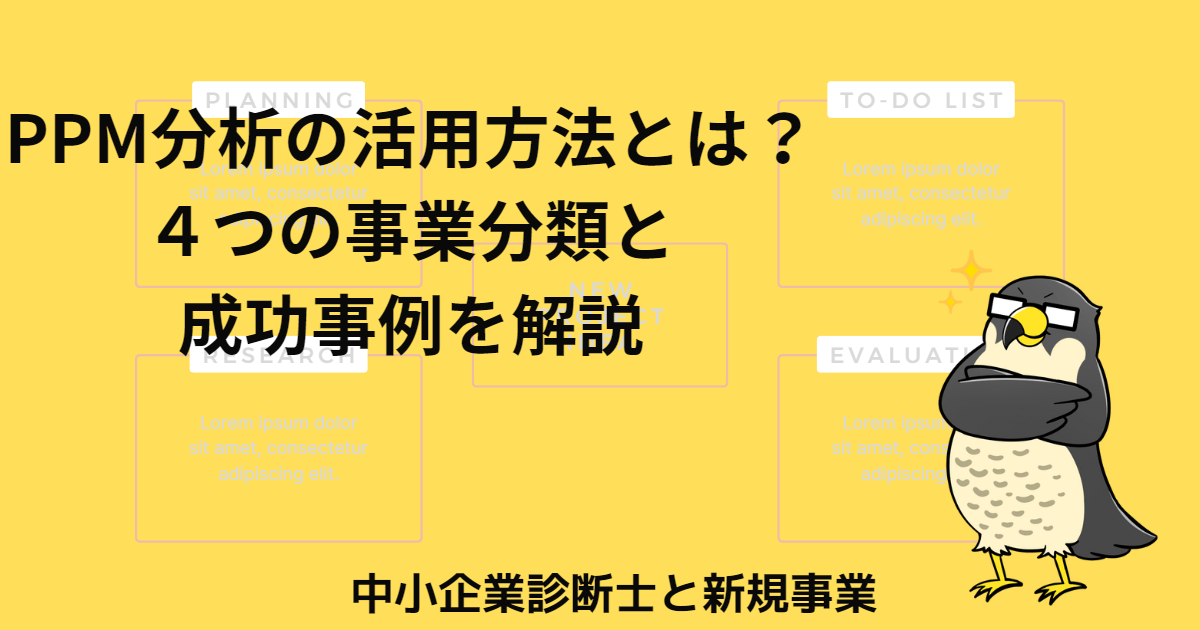


コメント