- 「理想の姿があるけど中々続かない」
- 「スキルをもう少し磨きたいけど上手くいかない」
仕事をしている中で、このように悩んでいる人いませんか?
そんなあなたにおすすめなのが「リコンソリデーション」です。
リコンソリデーションはスポーツ選手も利用しており、とても簡単な方法なので誰でも使えます!
今回はリコンソリデーションの概要や事例、組み合わせると効果的なインターリービング、リコンソリデーションをビジネスで活用する際の注意点を紹介します。
リコンソリデーションでスキルを上達させたい方はぜひ最後まで読んでください。
リコンソリデーションとは
リコンソリデーションとは、同じ練習を繰り返すのではなく、少しずつ微妙に変化を加えながら反復練習するという方法です。
大学の研究では、被験者86人を対象に以下の3つのグループに分けてリコンソリデーションに関する課題に取り組んでもらいました。
- 同じ練習を2回繰り返す
- 少し内容に変化をつけた練習を2回繰り返す
- 1回だけ練習する
その結果、「②少し内容に変化をつけた練習を2回繰り返す」グループの成績がトップでした。
しかも「①同じ練習を2回繰り返す」よりも、課題をやるスピードと正確性が2倍だったそうです。
この実験を通して、練習に少しだけ変化をつけると、脳が変化に対応しようと活性化して効率的に学習してくれるという結果が出ました。
反復練習という慣れた練習よりも脳が頑張ることでリコンソリデーションは少しだけ変化を付けることで脳がサボるのを防ぐということがわかります。
大リーグで活躍する大谷翔平選手も練習のなかで様々な重さのボールを投げているそうです。
これによって、投球動作の感覚を研ぎ澄ませて安定したフォームが身につけていると言えるため、リコンソリデーションを利用していると言えそうです。
リコンソリデーションの事例
リコンソリデーションは、以下のようなシーンでも活用できます。
リコンソリデーションの資格勉強への適用
資格勉強は長期的に勉強が必要ですよね。
リコンソリデーションを使えば集中力が継続し、いい影響を与えます。
例えば、問題形式を変えて実力試しをする、違う問題集やテキストで言い回しを変えた説明を聞くと新しい発見があるかもしれません。
リコンソリデーションのスポーツへの適用
先述の大谷選手のように練習に少しだけ変化を加える方法もあり、他にも道具を変える、立ち位置を変えるのもいいでしょう。
野球のバット、ゴルフクラブ、テニスのラケットなどで、道具を変えると重さが違う場合があるのでリコンソリデーションの観点からは有用です。
また、バスケットボールなどではシュート練習の立ち位置を少しずつずらして練習することで効果を発揮するでしょう。
リコンソリデーションの楽器への適用
楽器の練習の場合、ピッチ(速さ)を変えて練習してみましょう。
これはどんな楽器でもできる方法で、姿勢を変えるのもいい練習になります。
楽器によっては難しいかもしれませんが、姿勢を変えて練習してみてもいいでしょう。
ギターなどの楽器では、「座って練習する」「立って練習する」という変化を加えると効果的です。
リコンソリデーションとインターリービング
リコンソリデーションは、インターリービングと組み合わせることで大きな効果を期待できます。
インターリービングとは
インターリービング学習とは、何かを学習する際にあえて関連性のある違う科目を混ぜる学習法です。
例えば、数学の勉強するときに物理の勉強を挟む、日本史の勉強するときに世界史の勉強を挟むことです。
同じことを繰り返し勉強するよりも、インターリービング学習のように途中で挟み込む学習が定着率を上げるという結果が出ています。
これは「ツァイガルニク効果」による心理が働くからです。
「ツァイガルニク効果」とは、終えてしまった事柄よりも、途中で挫折してしまったり中断してしまったりした事柄のほうがよく記憶に残るという効果です。
学生時代のテストで解答できた問題よりも解答できなかった問題の方が記憶に残っていませんでしたか?
これは「正解したかった」という気持ちからツァイガルニク効果が生じているからです。
リコンソリデーションとインターリービングとのちがい
目的として、リコンソリデーションは「慣れを防ぐ」、インダーリービングは「忘れるのを防ぐ」ことです。
リコンソリデーションは少しの変化を加えながら反復練習を繰り返すことで慣れによる怠惰を防ぎ、課題に取り組む集中力がアップします。
インターリービングは交互学習することでツァイガルニク効果を働かせ、定着率をあげます。
この2つを組み合わせることで、集中力を持続させ、定着率を上げることが可能です。
英検の資格を取りたい時に、文法の勉強をやり続けるのではなく、長文・文法・単語・文法というように交互でやる(インターリーブ学習)、たまには場所を変えて勉強してみる(リコンソリデーション)ということを試してみましょう。
リコンソリデーションをビジネスで活用する方法
例えば繰り返し作業の仕事はいつか慣れが生じてしまい注意力が散漫になってしまうケースがあります。
注意力が散漫だと成果が出なかったり、ミスしてしまったりする可能性があります。
これを防ぐにはリコンソリデーションが効果的です。
環境に変化がないようであれば休憩時に散歩して外の空気を吸うだけでも気持ちがスッキリします。
カフェなどいつもと違った環境で仕事をやってみるのもいいですね。
また、定期的に職場の人とコミュニケーションをとることで繰り返し作業の中でも改善点が見つかったり、モチベーションに変化が生まれます。
このように同じ作業に少し変化を加え続けるだけでもモチベーションが維持されていきます。
リコンソリデーションを活用する際の注意点
リコンソリデーションの注意点は反復練習する時の変化の度合いです。
「脳が変化に対応しようと活性化する」がリコンソリデーションの特徴なので、脳が対応できる程度の変化を加えることが必要です。
大きな変化をつけてしまうと脳は新しいことをしたと認識してしまい、効果が半減してしまい、反復の効率が落ちるとされています。
ピアノを弾けるようになりたいと思ってリコンソリデーションする場合に、ミニピアノで練習するのとでは指の感覚が大きく違ってくるため、効果は出ません。
ある程度予測可能な変化で十分ということを覚えておきましょう。
中小企業診断士試験おすすめの通信講座
中小企業診断士のおすすめ通信講座を紹介します。低価格帯でコストパフォーマンスに優れたものがおすすめで、高価格帯の講座は含まれていません。
診断士ゼミナール

・詳しい解説付きの過去問題集7年分
・二次試験合格に必須の添削指導
・新しい暗記ツールの一次7科目穴埋めドリル
・合格お祝い金と3年間受講延長無料
スタディング(旧 通勤講座)

・AIを使った学習サポートが充実!AI学習プランは魅力的
・科目ごとの関係が明白な学習マップ
・AIによる実力スコア判定で成長を実感できる
まとめ
スキルを上達させるためは飽きずに集中力を持続させるかが大切です。
リコンソリデーションでは少しずつの変化を加えながら反復練習していくことで集中して学べます。
また、インターリービングと組み合わせればスキルを上達させることが可能です。
脳をサボらせないように、忘れないように変化を加えて勉強を頑張りましょう。

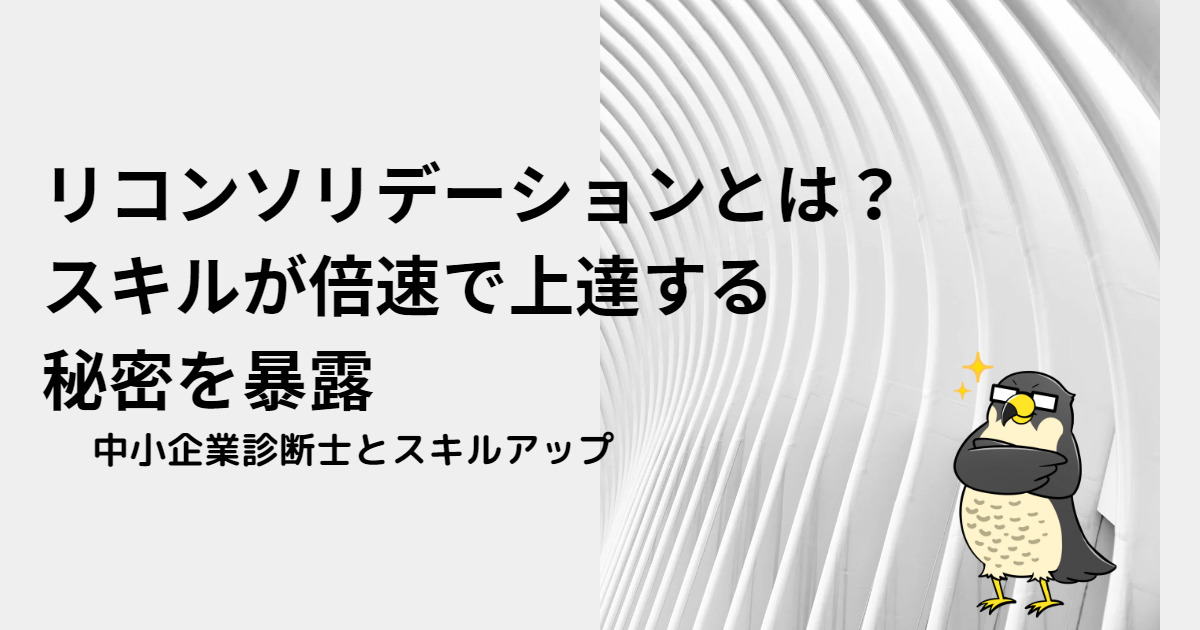
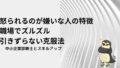
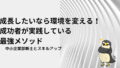
コメント