ソーシャルセリングとは、Facebook、Instagram、Twitter、LINEといったSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を使った営業戦略のことです。
「SNSって営業活動に使えるの?」
「SNSを営業に取り入れる方法は?」
今や日本人の8割近くの人が利用しているSNS。
そんなSNSを使った営業戦略「ソーシャルセリング」の初心者向けの運用法について、ご紹介していきます。
※SNSを活用した営業方法には、各サービスの広告を活用した方法もありますが、この記事では広告活用に関しては扱いません。
SNSは営業で使える!
SNSは、初心者でも営業で使える最強ツールです。
無料で使えるため、Web広告のようにコストをかける必要はありません。
また近年難易度が急激に高くなっているSEO(検索エンジン最適化)などの知識が無くても、コツやポイントを押さえれば目的に合わせて効果的に運用することができます。
顧客と気軽にコミュニケーションをとることができるのも、魅力のひとつです。
1.無料で利用できる
SNSは、会員登録をすればすぐに利用を開始できます。
気楽に始めることができるだけでなく、さまざまなサービスも無料です。
2.SEO等の知識が無くても運用できる
SNSに投稿する内容については、インターネット検索で上位に表示されることを目的とする必要はありません。
SEOの特別な知識が無くても、運用できます。
3.目的に合わせてアプローチできる
各SNSには、ユーザーの年齢層や趣味趣向に特徴があります。
その特徴を有効に活用すれば、商品やサービスを知ってもらいたい顧客層に、ダイレクトにアプローチできます。
4.顧客と気軽にコミュニケーションできる
気軽に顧客とやり取りができる「メッセージ機能」を利用して、投稿に興味関心がある人から質問を受けたり、個別に詳しく説明したりできます。
また、「ここだけの情報」というように、発信する情報に付加価値を付けることも、とても効果的です。
PRしたい商品やサービスが顧客側にどのように見えているのかは、投稿した記事につくコメントや「いいね」の数でダイレクトに伝わってきます。
投稿する内容の改善策を知る手がかりとして、役立てましょう。
ソーシャルセリングが注目される理由
営業で使えるSNSの特徴について、ご紹介してきました。なぜ、ソーシャルセリングが注目されているのでしょうか。
ここではその背景について、詳しくご紹介します。
ソーシャルセリングとは?
ソーシャルセリングとは、Facebook、Instagram、Twitter、LINEといったSNSを使った営業戦略のことです。
SNSを通じて、すぐにでも商品やサービスを必要としている顕在層と、いつかは顧客になるであろう潜在層にアプローチできます。
また、ユーザーは自分の疑問や悩みを解決してくれる「その道のプロ」をSNSで探す傾向があることも、注目すべきポイントのひとつです。
日本人の8割近くが利用しているSNSを、ブランディングや商品のPRといった営業活動に戦略的に取り入れていくことは、自然な流れだといえるでしょう。
情報収集方法の変化
GoogleやYahooなどのネット検索で情報を収集することは、今でも主流ですが、SNSの「ハッシュタグ機能」で、SNSの中で知りたい情報を収集する「SNS検索」を利用する人が増えています。
SNS検索とは、記事に付けられているハッシュタグをキーとして、無数にある投稿の中から自分が欲しい情報が掲載されている投稿を、ひとつにまとめて閲覧しやすくすることができる機能です。
SNSの利用者数の増加とともに、この検索機能を利用する人が増加していくのは明らかであり、こうした顧客の「検索行動の変化」を、営業戦略に活かさない手はありません。
費用対効果と情報拡散力
「費用対効果」と「情報拡散力の高さ」も、SNSを利用するメリットです。
会員登録は無料で、だれでもすぐに始めることができ、情報の内容によってはユーザーによって拡散され、より多くの人の目に触れることになります。
初期投資0円で効果が高いSNSを上手に利用すれば、普段接することのない顧客とのつながりが生まれ、ビジネスチャンスが拡がります。
人を感じることができる安心感
気軽にコミュニケーションできるSNSは、顧客との距離がグッと縮まるツールです。
質問に返答したり、もらった感想にコメントをしたりできます。
こうしたやり取りは、どんな人がこの商品やサービスを提供するのかを、顧客側が「感じ る」ようになり、「親近感」が生み出されます。
例えば、家や車といった、値段の高い大きな買い物をするとしましょう。
何を買うのかはもちろん、誰から買うのかも、重要なポイントになるのではないでしょうか。
知りたいことに的確に答えてくれるのか、安心して商談を進めることができるのか、信頼できる人なのか、購入した後のフォローはキチンとしてもらえるのかなど、同じ商品やサービスが提供されているなら、その人となりが分かっている人から買いたくなるものです。
そういう意味では、SNSでのコミュニケーションは、商談成立へのスタート地点だといえるかもしれません。
目的に合ったSNSの選び方
それでは、主なSNSのユーザー特徴と目的に合った選び方についてご紹介します。
導入を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
ビジネス層の利用が多く、実名での登録が必要なため、信頼性の高さが特徴です。
メインユーザーは、30~40代のビジネスマンなので、そこをターゲットとした商品やサービスのPRに向いています。
面識のある人同士のつながりが強く、口コミ効果も期待できます。
文章コンテンツよりも、写真や動画でPRできるのが特徴で、見た目の美しさや可愛さなど、ビジュアルにインパクトがある商品が向いています。
20~30代がメインユーザーで、買い物の手段としての利用する人も増えていることも、ポイントです。
他のSNSに比べて拡散性が低いですが、ハッシュタグ機能を使えば、情報をピンポイントで届けられます。
自分の今の気持ちを140文字以内で発信するSNSです。
スマートフォンとの相性が良く、気軽に発信でき、拡散性が一番高いのが特徴です。
トレンドに敏感な10~40代がメインユーザーなので、話題性が高く、トレンドを反映した商品やサービスのPRに向いています。
LINE
無料でチャットや通話ができるツールです。
他のSNSと比べてユーザー数が圧倒的に多く、幅広い年齢層が利用しています。
「友だち登録」の機能を利用すれば、興味関心がある人にダイレクトに情報を届けることができるだけでなく、チャットで個別にやり取りできます。
TikTok
BGMに合わせてアプリ内で作った15秒~3分の動画を、投稿できるSNSです。
メインユーザーは10代の若者で、バズりやすく、1度バズると他のSNSへの拡散効果も期待できます。
10代の若者に好まれそうな商品やサービスを、新しくて楽しい、もしくはマネしたくなるコンテンツで発信できれば、バズる可能性が高くなります。
「どんな商品やサービス」を「どんな年齢層に知ってもらいたいか」といった、ソーシャルセリングの目的やターゲットをまずは設定し、それに合った効果的なSNSを見極めましょう。
初心者ができるソーシャルセリング運用法
ここまで、営業で使えるSNSの特徴と、目的に合った選び方についてご紹介してきました。
では、これからソーシャルセリングを取り入れたいと考えている人は、何からどう始めればいいのでしょうか。
ポイントと一緒に、ステップごとにご紹介します。
step1 ソーシャルセリングの目的やターゲットを設定する
ご紹介したとおり、SNSによってユーザーの年齢層や趣味趣向といった特徴があります。
適切なSNSを選択できるように、どんな相手に何をアピールしたいのかを事前に整理し、ソーシャルセリングの目的やターゲットを明確に設定しておきましょう。
step2会員登録をする
利用するSNSの会員登録をします。
プロフィールは、どんな分野のどんなアカウントなのか、ユーザーに伝わるよう、分かりやすく簡潔に表示しましょう。
step3 まずは身近な人、面識のある人とつながる
まずは身近な人や面識のある人とつながる、もしくは知ってもらうことからはじめましょう。
企業で働く人なら、会社の㏋で告知してもらったり、リンクを貼ってもらったり。また社内で共有して、まずは身内からフォロワーになってもらうなど、さまざまな方法があります。
会社の理解があれば、名刺にアカウントへ飛ぶことができるQRコードを表記してもらうこともできるでしょう。
個人商店やお店なら、チラシやショップカードへのQR記載、また割引クーポンを付けて、友だち登録を促す方法もフォロワーを増やすには効果的です。
QRコードからアカウントにアクセスしてもらうために、名刺やチラシ・ショップカードを渡すときに「どんな情報を発信しているか」を、顧客にはっきりと伝えることが大切です。
step4 定期的に投稿する
フォローしても、投稿が無ければ顧客は離れていきます。
これが一番大変なことなのですが、投稿は定期的に、継続して行いましょう。
効果がすぐに出ない場合は、挫折しそうになりますが、定期的な投稿は遠回りなようで、実は一番確実な方法です。
最新記事だけでなく、これまでコツコツ投稿してきた過去の記事が、何かのタイミングでSNSの中でピックアップされ、注目されることがあるからです。
フォロワーは、フォローするメリットを感じられないと離れていきます。
商品やサービスのPRだけの投稿を続けるのは、営業色が強すぎて敬遠されるので気を付けましょう。
商品やサービスに対するアンケートを実施したり、商談のリアルな失敗談や商品開発の裏話を入れたりするなど、そこでしか得ることができない情報を盛り込んだり、投稿内容に変化をつける工夫も大切です。
個人商店やお店の投稿なら、プライベートな内容も入れてみましょう。
「趣味が一緒」「出身地が同じ」「考え方に共感」など、SNSを介した新しいつながりが、新しいビジネスチャンスのきっかけになることがあります。
ソーシャルセリングの注意点
ここまで、SNSを営業に取り入れることのメリットについてご紹介してきました。
運用するにはメリットばかりではなく、注意しなければいけない点がいくつかあります。
運用ルールを決めておく
情報はネット上に出てしまうと、拡散されてしまいます。
あとで何か大きな問題が発生すると、対応が非常に難しくなります。
企業で運用する場合は、担当者の選定、情報の取り扱いや運用方法など、ルールを決めておきましょう。
個人商店やお店なども投稿のルールを決めてから、SNSをスタートさせましょう。
つながりを強化するために使う
SNSは営業に使えるツールですが、初対面の人にバンバン営業を仕掛けるには向いてい ません。
なぜなら、ユーザーはそれを望んでいないからです。
しつこくアプローチするとブロックされたり、通報されたりします。
発信した情報を手がかりに、顧客側が少しずつこちらに近づいてくるというのが、ソーシャルセリングの醍醐味であり、最も望ましいカタチです。
発信する側と、それを受け取る側に「つながり」を生み出し、そのつながりを強化することで、将来的な顧客へと育てるツールであるということを理解しておきましょう。
中小企業診断士試験おすすめの通信講座
中小企業診断士のおすすめ通信講座を紹介します。低価格帯でコストパフォーマンスに優れたものがおすすめで、高価格帯の講座は含まれていません。
診断士ゼミナール

・詳しい解説付きの過去問題集7年分
・二次試験合格に必須の添削指導
・新しい暗記ツールの一次7科目穴埋めドリル
・合格お祝い金と3年間受講延長無料
スタディング(旧 通勤講座)

・AIを使った学習サポートが充実!AI学習プランは魅力的
・科目ごとの関係が明白な学習マップ
・AIによる実力スコア判定で成長を実感できる
まとめ
SNSは営業に使えるツールです。
ユーザーの利用率が増加傾向の日本では、ソーシャルセリングの重要性がますます高まってくるのではないでしょうか。
ソーシャルセリングの目的やターゲットを設定し、ゴールを見据えた戦略を立て、ユーザーの年齢層や趣味趣向といった特徴に合わせてSNSを選定し、運用していきましょう。
新しい営業戦略として、SNSをぜひ取り入れてみてください。

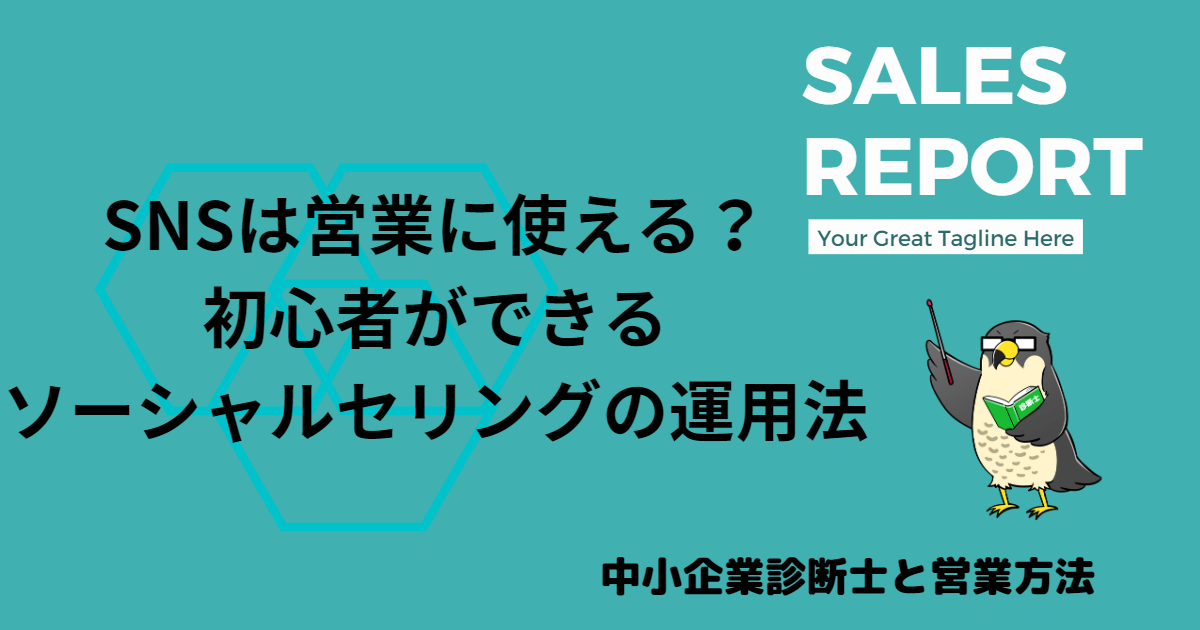


コメント