- やるべき仕事が多すぎて、どこから手をつければいいかわからない
- 誰がどんな仕事を進めているかリアルタイムに知りたい
- 仕事が進んでいる実感が湧かない
仕事をしている中で、このように感じたことはないでしょうか。
特に、複数人が関わるプロジェクトでチームマネージメントをする際に、感じることが多いと思います。
そんな時に役立つ方法として、スケジュールを視覚的に管理する「WIPボード」という手法があります。
この記事ではWIPボードとは何か、メリット、デメリット、活用方法、チームマネージメントへ適用した場合の効果を解説します。
マネジメントスキルを身に着けたい場合には、技術講座専門のJTEXがおすすめです。技術講座専門ですが、例えばトヨタ系のマネジメント手法やドラッカー、メンタルヘルスマネジメントなど、さまざまなマネジメントに関するスキルを身に着けることが可能です。
WIPボードとは
WIPボードの「WIP」はwork in processの略で「進行中の作業」という意味になります。
WIPボードはカンバンボードとも呼ばれており、トヨタ自動車が開発した手法です。
トヨタの生産工場の各チーム同士が意思疎通を図るために、必要なものや進捗状況を看板に書いて渡していたことが発祥です。
タスクや進捗状況をホワイトボードやパソコン上で可視化して、誰が見てもプロジェクトの進捗状況を瞬時に把握することができます。
WIPボードのメリット
まずは、WIPボードのメリットについて解説します。
作業の可視化ができる
WIPボードを活用する最大のメリットは、どのようなタスクがあるか、それぞれのタスクの進捗状況が可視化されていることです。
可視化されていることで誰が見ても、リアルタイムの進捗状況をすぐに理解することができます。
タスクの無駄をなくす
WIPボードではタスクを可視化しているので、重複しているタスクがあれば、仕事に取り掛かる前に気づき省くことが出来ます。
また、タスクの進行が遅れているメンバーもわかりやすいため、応援に入るなど早めに対処をすることができます。
業務を適切に割り振ることができる
プロジェクトの全体像が把握できるため、メンバー間での業務の偏りが把握しやすくなり、均等に仕事を割り振ることが可能です。
業務の偏りが無くなることで、効率的に仕事が進むと共に、精神的な不公平感も減らすことが可能です。
コミュニケーションが活発化される
WIPボードがきっかけとなり、各タスクに対するコミュニケーションが生まれます。
コミュニケーションが活発になれば、タスクを進めるためにさまざまなアイディアが生まれ、仕事が効率的に進むでしょう。
また、個人ではなくチームで働いるという意識が高まり、一体感が生まれやすくなります。
WIPボードのデメリット
続いて、WIPボードを活用する際のデメリットについて解説します。
タスクの重要度が把握しにくい
WIPボードは全体像を把握することには優れていますが、各タスクの内容や重要度までは把握しにくくなっています。
対策としては、仕事の内容や重要度をタスクの色や大きさで区別することがオススメです。
人によっては向き不向きがある
チームの一体感は生まれますが、マイペースに仕事がしたい人にとっては仕事に干渉されていると感じる場合があります。
個人の特徴次第で、すべての人に向いている方法ではありません。
各個人との声かけを大事にしながら、能力や性格に見合った仕事を割り振ることが重要になります。
WIPボードを構成する要素
WIPボードには7つの要素があります。
それぞれについて説明します。
視覚化された作業項目(タスク)
プロジェクトで対応する必要がある仕事を、1項目ごとに書き出したものです。
タスクは、できるだけ細かい内容にするなどルールを作ることで、業務規模のバラツキを無くすことができます。
また、優先順位を考え、わかりやすいように並べることもポイントです。
ステージ
ステージとはワークフローのことで、WIPボードの横軸になります。
「TO DO」「進行中」「完了」の3つが基本で、プロジェクトの内容に応じてアレンジすることができます。
このステージの間をタスクが1つずつ移動して、タスクの完了を目指します。
TO DO
仕事の内容が具体化されて、仕事を始める準備が出来た状態のタスクを置く場所です。
優先順位の高いものを上に置くなどわかりやすく工夫すると見やすくなります。
進行中
進めている最中のタスクを置く場所です。
メンバーの名前の横に進行中のタスクを置きます。
進行中のタスクがうまく進まない場合や進んでいない場合は声を掛け合い、早めに対策をします。
完了
終了したタスクを置く場所です。
進行中作業の上限
1人に対して同時に進行できるタスクを制限することで、仕事の偏りを防ぎます。
また、並行作業を減らすことで個々の仕事に集中できます。
作業の終了地点
基本的にはクライアントに商品やサービスが、提供される時が終了地点となります。
WIPボードの作り方
実際に仕事に取り入れる際の方法を説明します。
ステージを作成
作業の流れを考えて、左から順番に設置します。
基本は「TO DO」「進行中」「完了」ですが、「TO DO」「進行中」「確認中」「完了」などプロジェクトに応じて、アレンジできます。
タスクを可視化
タスクはできるだけ最小単位にするなど書き出し方のルールをつくり、タスクの仕事量のバラツキを防ぎます。
また、タスクの優先順位を考え、重要度順に配置するなど工夫するとよりわかりやすくなります。
タスクをステージに配置
はじめはすべて左端の「TO DO」に配置します。
タスクに取りかかった人は進行中へタスクを移動し、その後も完了までの間、1ステージずつ移動させます。
進行中の欄は上限をもうけた場合は、設定以上のタスクを配置しないように注意します。
WIPボードをチームマネージメントへ適用する効果
WIPボードを取り入れることで、チームマネージメントが向上しいい効果が期待できます。
情報交換ツールとして活用しやすい
WIPボードはシンプルな作りで理解しやすく、誰にでも使いこなすことができるため、メンバー共通の情報交換ツールとして役立ちます。
「プロジェクト全体がこうなっているから、今はこの仕事をして欲しい」など、WIPボードを見ながら、説明することで理解しやすくなり、ミーティングでもWIPボードを活用することで、問題点が見えやすく話し合いが進めやすくなります。
チームに一体感が生まれる
プロジェクトのメンバー全員が進捗状況を確認できるため、個人でのタスクが終わっても、他のメンバーへの声をかけや、助け合いを行うことができ、一体感が生まれやすくなります。
一体感が生まれることはプロジェクトの生産性をあげるには必要不可欠なことです。
中小企業診断士試験おすすめの通信講座
中小企業診断士のおすすめ通信講座を紹介します。低価格帯でコストパフォーマンスに優れたものがおすすめで、高価格帯の講座は含まれていません。
診断士ゼミナール

・詳しい解説付きの過去問題集7年分
・二次試験合格に必須の添削指導
・新しい暗記ツールの一次7科目穴埋めドリル
・合格お祝い金と3年間受講延長無料
スタディング(旧 通勤講座)

・AIを使った学習サポートが充実!AI学習プランは魅力的
・科目ごとの関係が明白な学習マップ
・AIによる実力スコア判定で成長を実感できる
まとめ
WIPボードは仕事のタスクや進捗状況を可視化して、プロジェクトの全体像を、誰が見てもわかりやすくする手法でした。
プロジェクトの進捗状況を可視化することで、チームの一体感が生まれやすくなり、生産性が上がります。
また目標に向かって進んでいることがわかりやすいため、モチベーションが上がりやすくなることも期待できます。
WIPボードを仕事に取り入れることは、チームマネージメントにおいてプラスの効果をもたらしてくれるでしょう。
チームマネージメントに悩んだ際は、WIPボードの活用を検討することをおすすめします。

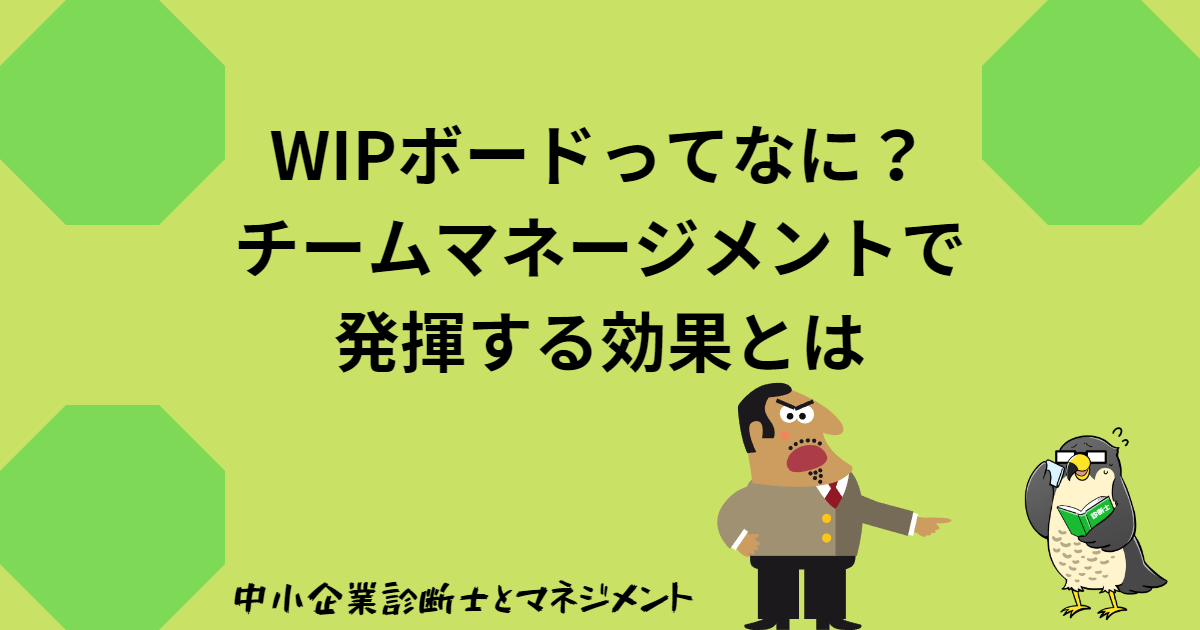
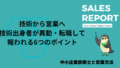

コメント